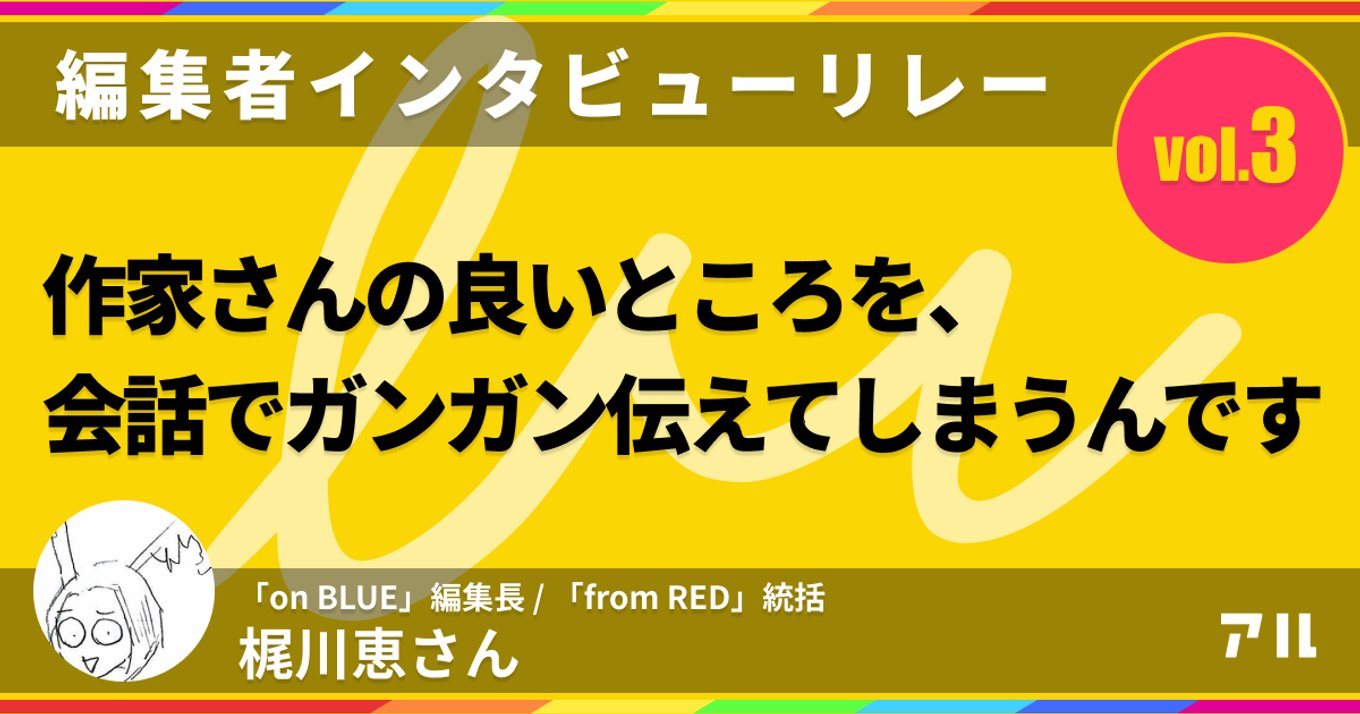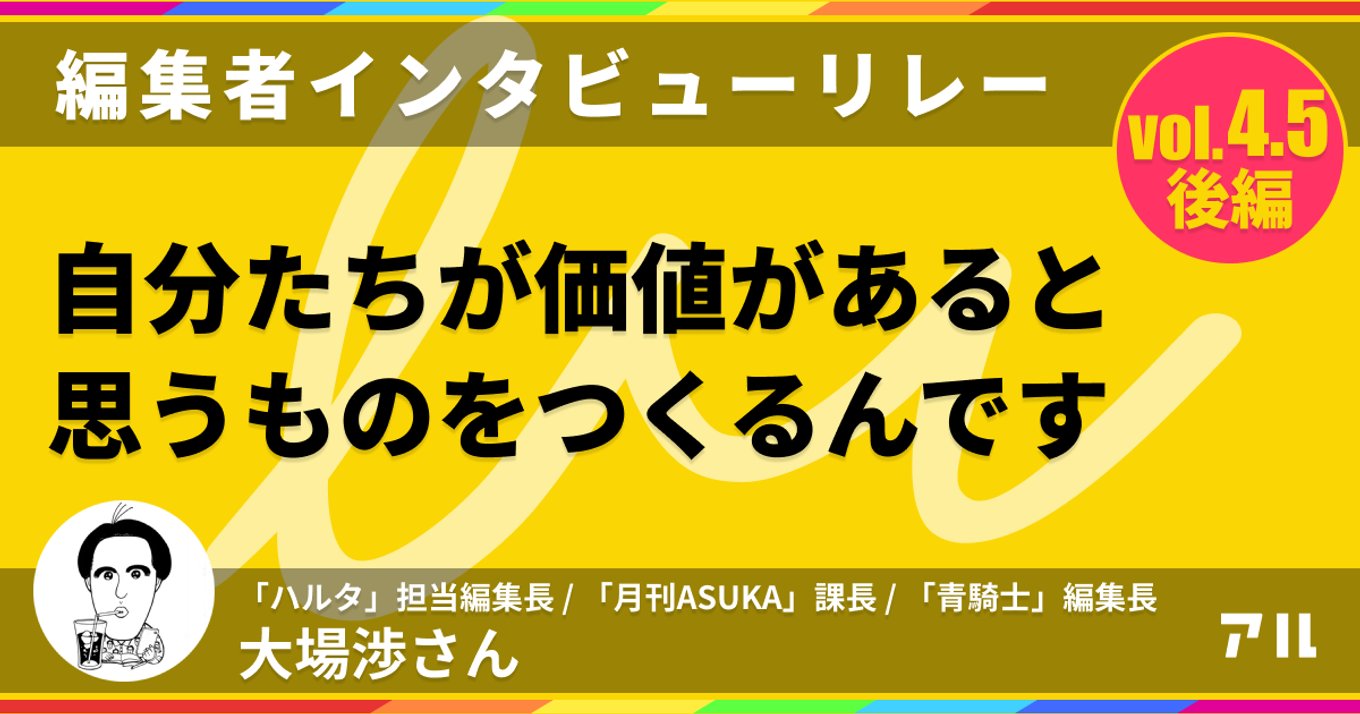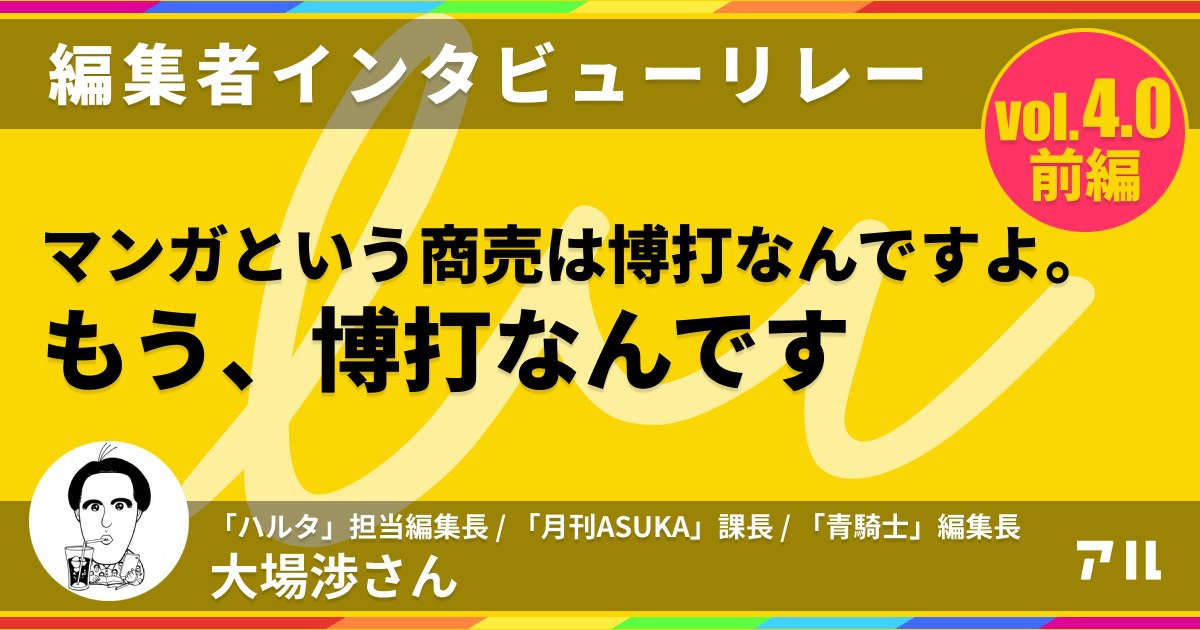
マンガ編集者さんって、本当にいろんなタイプの方がいらっしゃいます。それぞれヒット作を世に送り出すための仕事術に個性があり、お話をお聞きするのが本当に面白いんです。
「編集者インタビューリレー」Vol.4のインタビューは、なんと2時間半もの長丁場となったため、前後編の2本立て。話を伺ったのは、長らく「ハルタ」編集長を務めてこられたKADOKAWAの大場渉さんです。
アスキー(現在はKADOKAWA)に新卒入社し、「週刊ファミ通」、「月刊コミックビーム」での編集業務を経て、新雑誌「Fellows!(現ハルタ)」を創刊。
ハルタの初代編集長として『乙嫁語り』(森薫)、『乱と灰色の世界』(入江亜季)をはじめ数多くの作品を立ち上げた後にその座を退かれました。
現在はハルタ、「月刊ASUKA」で編集業務をこなしながら、2021年4月に創刊される新雑誌「青騎士」を準備されています。
そんな錚々たる来歴を持つ大場さんが、コミックビームの源流となった秋田書店に根付くマンガ編集の考え方から、それを引き継いだハルタのある編集方針、マンガ編集という「博打」を見極めるペンタッチの話まで、さまざまな角度から「マンガ編集」について語ってくださいました。
連載のVol.3はこちら。女性向けマンガ誌「FEEL YOUNG」で『違国日記』『中学聖日記』『いいね!光源氏くん』ほか数多の作品を担当し、BLマンガ誌「onBLUE」の創刊編集長を務める梶川恵さんにインタビューを行いました。
編集者さんのプロフィール
大場渉
1997年にアスキー(現在はKADOKAWA)へ入社。あすか編集部とハルタ編集部の責任者で、2021年から新漫画誌「青騎士」を創刊する予定。著書を全冊読破した作家は、谷口ジロー、南條範夫、外山滋比古。
目次
- ホテルマンになるつもりが、OB訪問をきっかけに編集者へ
- コミックビームの源流はゲーム制作会社・遊演体と秋田書店
- マンガの売り上げとマンガ家の実力は切り離して考える
- 森薫先生との出会いと、『エマ』連載のきっかけ
- 「ペンタッチ」を持っていて売れないマンガ家はいない
さらに見る
ホテルマンになるつもりが、OB訪問をきっかけに編集者へ
ーー今日はよろしくお願いいたします!まず、大場さんはどういった経緯で編集者になられたんですか?
学生の頃に5年ほど飲食店でアルバイトをしていて、元々はサービス業への就職を考えていました。アルペンスキーという競技スキーをやっていたので、ずっとお金がないんです。夏にバイトして冬に使う、という。
ずっとアルバイトしている大学生という感じでした。飲食を中心に3件くらい掛け持ちしていて、ホールに立つのがとても楽しいから、その延長線上で仕事を考えたのが大学2年生のときです。最初はホテルマンになりたいと思っていました。
ーーホテルマンですか!今とは全然違うお仕事…。
でも、当時…90年代の終わりは氷河期と言われていて、就職活動が上手くいかなくて。縁故採用も探したのですがどこにも入れないから、ホテルは無理だと思って。
そんなときに編集者をしている大学の先輩に会う機会があったんですよ。それまではマンガに全く興味がなくて、「マンガってオタクっぽくて気持ち悪い」くらいのイメージで(笑)。
ーー強めの偏見だ(笑)。そういう時代だったんでしょうか。というか、それまでマンガは全く読んでいらっしゃらなかったんですか?
そうですね、高校生くらいから体育会に入っちゃうと、マンガなんて読まない。それがその人に会ってみたら、想像と違って魅力的な人で面白かった。
それまで、サラリーマンの人ってお堅くて嘘ばっかりつくなって思っていたんですが、こういう、あまり知られていなさそうな仕事なら面白そうだなって。それから他の出版社の人も紹介してもらってOB訪問をしていったら、出版界は肌が合うなと。ここだ、ってなった。
ーー実際に現場の人に会ってみたらイメージが変わった。
出版社の編集、特にマンガって思って、就職活動をして受かったのがアスキーでした。それで入社前にもう単位を取り切っていたので、人事に頼んでコミックビームで半年間アルバイトをしていたんですよ。
そうしたら本採用のとき、1997年にコミックビームが休刊するかもしれないという話になり、なくなる部署に新卒はやれないからと言って、最初は週刊ファミ通に配属されたんです。
ーーああ、そういうわけで週刊ファミ通に。元々マンガに興味がなかった大場さんが、そこまでマンガに惹かれた理由って何だったんですか?
最初にOB訪問をしたのが、講談社の「BE・LOVE」をやっていた宮本さんという方で。マンガが大好きで、マンガの力を信じていて、真剣に仕事へ打ち込んでいる姿が印象的だったんですよ。
ーーそれから他の編集者さんにもお会いしたんですよね。
そうですね。その次に当時、小学館の「ヤングサンデー(週刊ヤングサンデー)」をやってた西坂さんという人に会って、西坂さんは色々な連載を起こしていたんですけど、グラビアページも担当なさっていたんです。
西坂さんも、ものすごくマンガが好きで自分がやっている連載に打ち込んでる一方で「マンガなんてくだらないと思わない?」みたいに言ってくる、熱血と冷笑、ふたつの思いがある人で。
ーーおお。
それが大学生ながら、真剣に生きている人間の姿に見えたんですよ。就職に至ったのは、その二人の影響ですね。で、あとはマンガを知らなかったからこそ、楽勝だぜ的な。どうせやれば簡単だろう、という大学生らしいなめた期待もありました(笑)。
ーー実際に仕事としてやってみられて、どうでしたか?
簡単(笑)。マンガの編集は本当に楽な商売ですよ。
ーー(言い切っちゃうのすごいな…)
コミックビームの源流はゲーム制作会社・遊演体と秋田書店
ーー改めて大場さんが担当してこられた作品を色々と読ませていただいて、やっぱりハルタで掲載されている作品って独特の色があるなと。その辺りは創刊された大場さんの方針なんですか?
いえいえ、歴史です。元を辿ればその昔、遊演体の流れを組むアスキーのマンガ出版に、ファミ通が載せてきたマンガ、そして秋田書店から移ってきた編集者の3つが混ざり合ってコミックビームが始まったんですよ。
ーーえっ、そんな経緯だったんですね。
そうです。元々95年に『モンスターメーカー』の連載をしていた「月刊アスキーコミック」と、オリジナルのマンガが中心の「ファミコミ」が合体して月刊コミックビームになり、奥村(勝彦)さんが2代目編集長になった辺りからオリジナルのマンガづくりに力を入れるようになっていって。その96年に僕がアルバイトで入ったんですよ。
ーーそんな流れだったんですね。
入ったばかりの頃は若くてやんちゃな編集部で。会社でずっとオンラインゲームをやり続けて家に帰らない先輩もいたし、フロアーでサッカーしている人たちもいました。マンガの担当を1本もしていない編集者が何人もいて。
ーー時代を感じるというか、なかなかの不良サラリーマンですね…(笑)。
そんなこんなであまり仕事しない編集者たちがどんどんいなくなっていったんです。僕は残った(笑)。奥村さんはまともなマンガづくりのやり方を、何もないアスキーという会社に持ち運んできた人なんです。
ーーめちゃくちゃな環境だ…。そんな中で大場さんは、どうやってマンガの編集を学んでいかれたんですか?
コミックビームはものすごく貧乏な部署だったので、赤字を出したら翌年には廃刊という、とても厳しい雑誌だったんですよ。そもそもアスキーはコンピュータやゲーム系の会社だったんで。だから毎期黒字にしなきゃいけないんですけど、そんなにメジャーな雑誌じゃない。
だから、曽田正人さんの短編集を出したり、柴田亜美さんのファミ通の連載をまとめて単行本を出したりして、ビーム以外の力でしのぐしかなかったんですけど…元の質問は何でしたっけ、どうやって学んだかですか。
ーーそうですね。どういう風に学んでいかれたのか。
奥村さんから最初に言われたのは、「マンガ家に締め切り以外に嘘をついてはいけない」ということ。それは、どんな嘘も絶対にだめ。後はおもれーマンガをつくれ、ということ。
結局、僕は8年半コミックビームにいたんですけど、その間1回も売れるマンガをつくれとは言われなかったんですよ。それが今でもずっと残ってる。
ーーおもれーマンガをつくる。
全く同じことを秋田書店で「チャンピオン(週刊少年チャンピオン)」の編集長をやっている武川(新吾)さんも、一つ前のチャンピオンの編集長だった沢(考史)さんも、結局おもれーマンガをやったやつが食えるんだよ、みたいに言う。おもれーマンガをやったら売れる、それは秋田書店流派で。
ーー秋田書店流派!
『バキ』を出した編集部が『弱虫ペダル』を出したり、また次の担当が『BEASTARS』をつくったり。本当、秋田書店流派っていうのは一撃必殺。
なんていうか狙ってるサイズが他のサイズと違うんですよ。ホームランバッタータイプの編集者が多い出版社だと思います。
ーー確かに、秋田書店さんの作品ってドカンと売れるものが多いイメージがあります。まとめると、大場さんにもコミックビームの考え方が根付いているというか。
だから、コミックビームのときに8年半ずーっと考えていたのは、とにかく面白いマンガをやるんだ、大きいところを狙うんだっていうこと。それは金儲けをすることとはまた別の意識なんですけど。
マンガって売れるとぐらついちゃうんです。編集部も作家も。100万部くらい単行本が売れると、自分たちに100万部の実力があるんじゃないかと勘違いしちゃう。
あるなら、それはそれでいいんですが、実力と実売に差が開いていくとマンガづくりの土台がぐらつき始めちゃう。そういうときは、周りの作家と一緒に必死に抑えたりします。売れた部数が僕らの実力じゃねえよなって。
ーーおお、そんなことが。
おもれーマンガをつくること、ただそれだけでいいはずなんです。今つくっているマンガは5万人くらいなら楽しませられる、それなら5万部の連載をやって、次、狙えるなら20万人を狙おう。
そう考えればいいのに、一発目から20万部売れちゃったりする。うっかりお金が入って舞い上がっちゃったりもする。そんなとき、先輩マンガ家が、ああしたらいい、こうしたらいいと舞い上がる気持ちを抑えてくれたりするんです。
マンガの売り上げとマンガ家の実力は切り離して考える
ーー同じ雑誌の作家さん同士で、そういう風に支え合うというか、助け合われているんですね。
ハルタは、金と実力を切り離すって考え方を大切にしているので。
ーーここまでお聞きして、マンガが売れることとマンガ家の実力が別っていうのが少しピンとこなくて。
別だと思ってきました。それこそ、アスキーからエンターブレイン、そしてKADOKAWAと、3つの会社に渡って同じマンガ商売を続けてきましたから。
条件が買い切りだったアスキー時代、中規模出版社のエンターブレイン、そして「04」コードを持つ大手のKADOKAWA。会社が変わるごとに、世の中からの扱われ方が体感的に違います。
ーーおお、どういうことでしょう?
最初に感じたのは100万部を超えるコミックスが出たときでした。エンターブレイン時代はどうしても100万部以上売れる作品はつくれなかったんです。
どうやっても書店の棚が取れない。エンターブレインっていう出版社に対して、世の中がそこまでマンガの出版を求めていないんですから。
ーーつまり、エンターブレインが出した本は、書店が「売れる」と信用してくれなかった?
エンターブレインだと100万部つくれなかったのに、KADOKAWAになったらマンガで100万部出せるんだもの。なんだよー、って思いましたよ。それまではマンガの実力で100万部の作品をつくってやる!って思っていたんですけど。
ーーマンガ家さんの実力以前に、出版社が築いてきた信用という要素のほうが大きい。
そうですね。だから実力とセールスは関係ないと思っています。
ーーなるほど。
もう一つは、あんまり言いたくないですけど、大切なのは累計発行部数じゃないと思ってるんです。落ち幅じゃないか。
1巻から2巻でどれくらい読者が離れて、2巻から3巻でまたなんぼ、っていう落ち幅が商売では大切なんです。それを分かっていないと上手くいかない。
ーー落ち幅、ですか。
例えば地道にコツコツ売ってる『乙嫁語り』とかは本当に売り上げが落ちないんですよ。それは作品というよりも作家で売る商売になっているからで、目指すべきはそこだけだと思うんです。
そうじゃないマンガは、例えば何かの宣伝で紹介されたりして一時的に売り上げが伸びた後、その次の巻でぐっと落ちたりするんです。最大で25%くらい落ちる。2巻まで持っているけど3巻は買わないみたいな人がたくさんいるんです。
ーーだから、累計発行部数だけではその作品の本当の人気を判断できないと大場さんは考えられている。
こういったこと、編集者でも分かってるやつはちゃんと分かってます。けど口に出して言う人はあんまりいないかな、分かってる人は他人の作品にまで言わないから。
ーーそれはまあ、言いづらいですよね…。
あるところから上に行くとマンガ編集って謎の凄みが増してくるんですよね。尊敬するしないとかじゃなくて、人としてキャラがめちゃくちゃ濃くなる。
こういったことをいちいち口にしないでも、ただひたすらおもれーマンガをつくり続ける編集者になるから。「アフタヌーン」(講談社)の編集長をやってる金井(暁)さんとか「サンデー(週刊少年サンデー)」(小学館)の市原(武法)さんとかもそうで、若い頃も編集長になってからもヒット作を出しまくる。
『結界師』と『いでじゅう!』をやりながら、『信長協奏曲』を起こしたりする。それはここがマンガだっていうセンサーを張ってるんです。彼らはみんな分かっているんですよ、ここに来たらマンガだねって。
ーーなんかそれは、言語化できない感覚みたいなものに近いんですか?
どうなんでしょうか、僕自身は全部言語化していますし、多くの編集者は大体みんな言語化してるんじゃないですか、自分なりの言葉で。感覚でやってるのは奥村さん、沢さんくらいだと思う(笑)。
森薫先生との出会いと、『エマ』連載のきっかけ
ーーそういうマンガ編集のノウハウをしっかりまとめているかどうかって、編集部によってバラバラだと聞くんですが、個人単位で違う感じなんでしょうか?
マンガという商売は博打なんですよ。よく言うじゃないですか。でも、そもそも博打を打ちたい会社員があんまりいないんです。もう、博打なんです。
舟券を買ってるときと一緒で作家を信じるしかない。読み切るんです。しかし来ない(笑)。何やってんだよ!って、今日は11月23日だろ、1と2と3は必ず絡むはずだろ!って(笑)。
でも来ない。ときどき大当たりする。ほら、自分の読みは当たってた。そういう感じなんですよ。
ーーめちゃくちゃ当てずっぽうじゃないですか!とは言いつつ、入江亜季先生や森薫先生を見出されたという大場さんが何を見ているのか、やはり気になります。
そうですね…。高校3年生のときに、パソコン通信ってのに手を出したんですよ。「ニフティーサーブ」というのにはまって、毎晩遅くまで読んだり、書き込んだりしていました。
同質性が高くてかつクリエイティビティにあふれていて。顔文字、アスキーアート。創意工夫を凝らした無駄なエネルギーが満ちた場所。
ーーおお…。
そのパソコン通信の人たちが、同人誌即売会があるからって連れて行ってくれたんですよ。それからずっと長く即売会に張っていて、ファミ通から戻ってきた27歳のときに即売会で見つけたのが、森薫さんなんですよ。
ーー出会いは同人誌即売会だったんですね。
でも当時はまだ、即売会から作家を連れてくることは出版界ではタブーな時期だったんですよ。もっと昔はありました、奥村さんも入ったばかりの沢さんをコミケに連れて行ったりして。でも、僕がマンガ編集を始めた90年代末はほぼタブーになっていて。
ーータブーですか。
『蟲師』の漆原(友紀)さんが連載を始めたときも、増刊だったしペンネームも変えてるから最初は分からなかったし。同人誌のペンネームでそのままやるっていうのはなかなか珍しかった。同人は遊びだったんです。
ーープロが本気でやっているところに遊びで入ってくるな、みたいな空気だったんですか?
というか、全然上手くなかったんです。
ーー今の状況からは想像できないですね。
森薫さんの話に戻すと、最初はビームの巻末にちょろっと4コマを載せるコーナーがあって、そこで描いてたマンガ家が逃げたんですよ。あいつがいなくなった、誰かいないかってなったとき、森薫さんがWebサイトでやっていた4コマが面白かったので声をかけたんです。
ーーあれ、最初は4コマの予定だったんですか。
それが、同人誌もやってるんですよって言うから見せてもらったら、こりゃいけるなって。まだ23歳だったんですけど。それで奥村さんに持って行ったら、まずは読み切りからやってみようって。
ーー順当ですよね。
なんだけど森さん、読み切りとか描けないですよって言うんです。同人誌なんて全部読み切りなのに(笑)。
だから奥村さんのところに行って、「読み切り描けないんですよ、森さん」「そしたら連載か」「連載しか描けないって言ってます」「しゃあないのう」って(笑)。それで『エマ』で連載デビュー。訳のわからん時代だったんですよ。
ーーすごい、勢いで決まったんですね(笑)。ちなみに「こりゃいける」と思われたのは、どういった点が?
それはずっとビームのやり方と同じで、「今はない、だけど求められている」っていうマンガだったから。これをやったらウケる、でも今はない、そこを狙って商品をつくるだけです。
ーーだけっておっしゃいますけど、めちゃくちゃ難しそうな …。
だから出てるマンガを全部読むんですよ。今もすごい読んでるんですよ。
ーー(さらっとすごいことばかり言い切る人だな…。)
「ペンタッチ」を持っていて売れないマンガ家はいない
ーー少し話の筋を戻すと、博打うちとして、森先生や入江先生のどういうところを見ていたのかが気になるんです。
僕の場合は、ペンタッチなんです。大体の編集者はマンガを構成する要素を漠然と捉えるんじゃなくて、細かい要素を詰めていくんですよね。それは人によって違うんですが、僕は線を見るのが好きです。描線の美しさ。
森さんはペンタッチを持っていたんで。入江さんもそうですけど。ペンタッチがある作家で売れない人はいないですし、ペンタッチが絵をつくっていくんです。
ーーペンタッチ…。
難しい話ですが、作品に載る線で無駄な線って一本も引いちゃだめなんです。これは昭和からの教えで。シャカシャカシャカって誤魔化した描き方をしたらだめなんです。
越路吹雪さんとか布施明さんとか誰でもいいんですが、昭和歌謡でぱっと名前が出てくる人って一音一音を完璧に歌えるじゃないですか。それと同じです。
ーーこれしかないっていう線を正確に引けることですか。
芸能の究極はそこなんで。小田和正さんとかサザンの桑田(佳祐)さんとか、歌が上手い人は捨てる音がないんですよ。全ての挙動を制御している。それはお笑いもそうだし、スポーツマンもそう。
だめな野球選手は負け試合は流しちゃうけど、イチローとか違うじゃないですか。バッターボックスに立った瞬間に会場がイチローモードになるんですよ。もちろん悠然と出てくるんですよ。これが嘘偽りのないホームランバッターなんだなって。
ーーそれはマンガ家においてはペンタッチだと大場さんは考えている。
あだち充さんもそうだし、高橋留美子さんの美しい線が好きな人はペンタッチが好きなんですよ。絵柄じゃないと思う。
ーーそのペンタッチの要素って、習得できる技術なんでしょうか?それとも天性のもの?
技術です。Gペンでもなんでも、右腕の筋肉を鍛える。線を引き続けるとマンガ家用の右腕になってくる。
ーーマンガ家用の右腕!
僕が知るマンガ家は多くの場合において、過去を遡っていくと親からあまり興味を示されていない。3姉妹の3番目に生まれたとか、両親が共働きとか。構える親って子どもに習い事をさせたり、勉強の進捗を確認したりしちゃう。
でもほったらかしで育てられると、一番易きに流れるから、学校に行って絵を描いてるんですよ。授業中も絵を描いて、休み時間も絵を描いて。帰りも図書館に行って本を読むか絵を描くかの二択で。
それを小学生、中学生、高校生くらいまでやると同世代の中で圧倒的に絵が上手くなる。それが褒められるようになって、自分は絵に才覚があるんだなって感じるようになるんです。
ーーおお…。
それから同人誌即売会に行ったり、美大を志望して落ちたり受かったり。どっちでもいいです。それがマンガ家のど直球コース。
ーーその過程でペンタッチが磨かれていく。
漫然と線の太い細いを考えない。なぜ太いか、その太さはどのような美しさになるのかを考える。そうやって腕前を鍛えていって、一本一本良い線を描きましょうと。
ーーなるほど。
技術は知識と経験からなります。たくさんマンガを読み、たくさんマンガを描くこと。一つひとつ、技術を自分のなかに積み上げていくこと。
線だけじゃなく、画材や日本語の一文字一文字、枠線や吹き出しとは何か。マンガを構成するすべてのものを、一つずつ獲得していくこと。もう、それだけです。
2時間半にも及ぶ大場さんのインタビュー、前編はここまで。記事の後編はこちら。
Fellows!(現ハルタ)と新しく創刊される青騎士それぞれの立ち上げのきっかけ、作品づくりで大切にされている「ロングライフ」というテーマ、「根っからの商人」だという大場さんが編集者という仕事をどう捉えているかまで、盛りだくさんです。